朝倉宗滴【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

朝倉宗滴とは戦国時代の武将。越前朝倉氏三代(朝倉貞景・朝倉孝景・朝倉義景)に仕え、一族の宿老として当主を補佐し、自身は朝倉家総大将として各地を転戦してその武名を轟かせた名将です。
本名は教景。しかし法名である宗滴の名の方がよく知られています。
大名物・九十九髪茄子を所有していたことでも著名ですね。
今回はそんな朝倉宗滴を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!
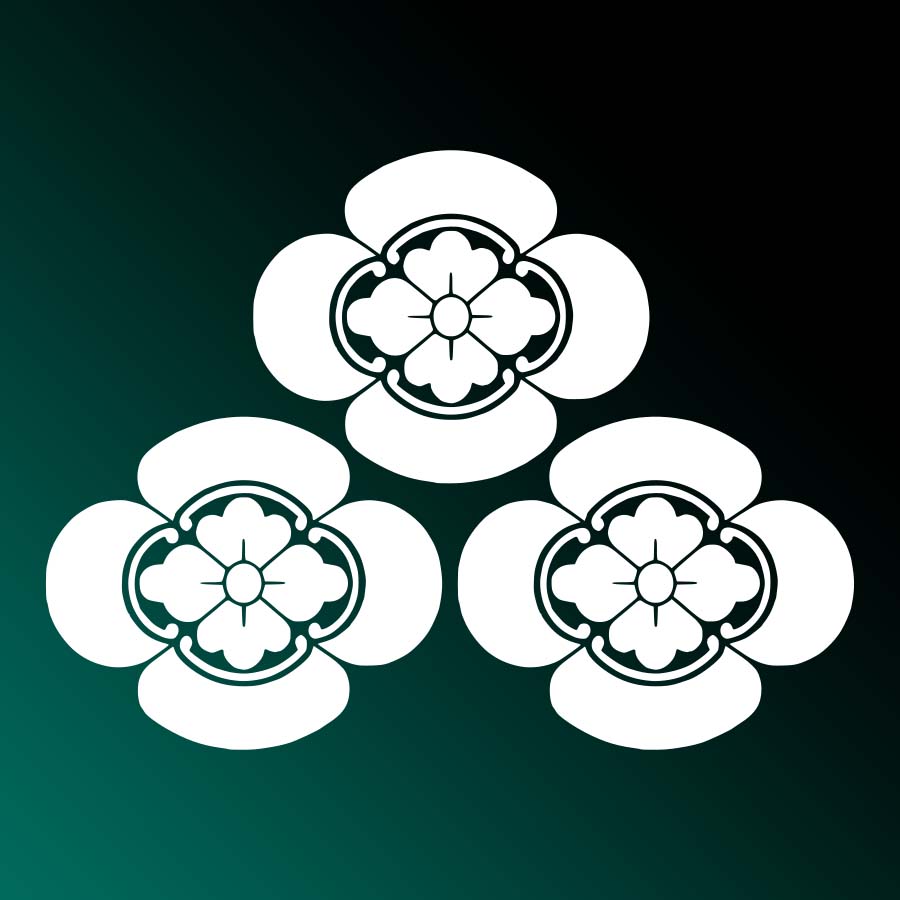 |
|
| 生年 | 1477年(文明9年) |
| 没年 | 1555年(天文24年9月8日) |
| 改名 | 小太郎⇒教景⇒宗滴 |
| 別名 | 太郎左衛門尉 |
| 主君 | 朝倉氏景⇒朝倉貞景<⇒朝倉孝景⇒朝倉義景 |
| 氏族 | 朝倉氏 |
| 家紋 | 三盛木瓜(みつもりもっこう) |
| 親 | 父:朝倉孝景(英林孝景) 母:桂室永昌大姉 |
| 兄弟 | 氏景 景明 孫四郎 景総 教景(以千宗勝) 時景(景親) 景儀 教景(宗滴) |
| 妻 | 朝倉景冬娘 |
| 子 | 蒲庵古渓 養子:景紀 |
信長の野望での朝倉義景
信長の野望・大志での能力値

| 信長の野望 大志 | |
|---|---|
| 統率 | 93 |
| 武勇 | 90 |
| 知略 | 90 |
| 内政 | 74 |
| 外政 | 83 |

朝倉宗滴といえば、『信長の野望』シリーズの中にて出没するチート爺様の一人として有名ですね。
そして見よこの能力!
90越えの能力が三つもあり、一番低い能力でも内政の74、外政も83と高く、武勇だけの猪武者でないことが分かります。
あの朝倉家の中では異質な存在ですね。
まさに朝倉家の命運は、宗滴一人の肩にかかっていたといっても過言ではないでしょう。
ただ管理人が初めて手に取って遊んだ『信長の野望 武将風雲録』では、開始早々に死亡するというインパクトのある登場と退場をする武将だったので、妙に印象に残っているのを覚えています。
宗滴が生きている数ターンのうちに、隣国のどこかを併呑できるかどうかが、朝倉家で攻略するためのカギでしたからね。
信長の野望・新生での能力値

| 信長の野望 新生 | |
|---|---|
| 統率 | 92 |
| 武勇 | 86 |
| 知略 | 91 |
| 政務 | 73 |

初期のシナリオにおいては活躍してくれるものの、やはり寿命が天敵。
しかし今回は朝倉宗滴亡きあとの後半のシナリオにおいて、宗滴に匹敵するチートな武将が配下にいますので、今作の朝倉家は宿敵織田家に一矢報いることができるかも、ですね。
とはいえ、朝倉宗滴はどうしてこうも評価されているのか。
それを宗滴の一生から紐解いてみたいと思います。
誕生から敦賀郡司まで
朝倉家の嫡男として
朝倉宗滴は1477年(文明9年)、朝倉敏景(朝倉孝景)の末子(八男)として誕生しました。
ということは、あの天下一の極悪人の末っ子だったというわけです。
八男ではあったのですが、八男ってそれはないでしょうということで、どうも父親である敏景は宗滴のことを嫡男として考えていたという可能性が指摘されています。
というのは、宗滴は最初「小太郎」と名乗っており、その後「教景」って名乗るようになるのですが、この「小太郎」は父・孝景も名乗っていた名前でり、「教景」は曽祖父である教景、祖父である家景、そして父である敏景が一時的に名乗っていた諱でもあります。
いかにも後継ぎにしたい、っていう孝景の気持ちが名前の変遷からも読み取ることができるというわけです。
朝倉家一門ではその名前を名乗る際に、「景」の字が使用されるのですが、嫡流はこの「景」の字を下につけるもので、それ以外の一門の人物は上につけるという慣習がありました。
宗滴の諱である「教景」はその慣習に則っており、そのため嫡男として遇されていたとも考えられています。
たとえば後で宗滴と謀って謀反を画策する兄・朝倉景総などは、朝倉家を出奔後に元景と改称し、いかにも自分が嫡流である、みたいなアピールをしていることからも、かなり名前というのは重要だったことが窺えますよね。
しかし敏景はどうして宗滴に対してそこまで期待したのでしょうか?
それはもちろんわかりませんが、しかしいつの世でも末っ子は可愛がられるもの。かどうかはともかく、宗滴の潜在能力を見抜いていたからかもしれませんね。
しかし父・敏景は1481年(文明13年)に死去します。
朝倉宗滴はこの時4歳。
年齢的にも家督を継ぐことは不可能であり、その地位は兄である氏景が継ぐことになったのです。
さすがに4歳では、とは思いつつも、のちの世で筒井順慶などは2歳で家督を継いでいたりもしているんですけどね。
とはいえ兄・氏景も十分に優秀な人物だったこともあり、家督継承は滞りなく行わたようでした。
朝倉景豊の謀反
1503年(文亀3年)、敦賀郡司であった一門の朝倉景豊が謀反を画策します。
この朝倉景豊とは如何なる人物かといえば、宗滴の父である朝倉孝景の弟・朝倉景冬の嫡男です。
要職である敦賀郡司を任されていたのですが、1495年(明応4年)に景冬が死去したことで、景豊が後を継いでいたのでした。
つまり、宗滴の従兄弟というわけですね。
しかも両者はそれだけの関係ではなく、景豊の妹たちはみんな朝倉一族に嫁いでおり、宗滴もその一人でした。
朝倉景豊の姉妹は朝倉宗滴を初め、堀江景実、鳥羽景富、青蓮華近江守ら朝倉一族に嫁いでいたといわれています。
要は従兄妹でもあり、妹婿でもあって、つまり義兄弟でもあるという、密接な関係だったわけですね。
とはいえ景豊はどうして謀反を起こそうとしたのか。
そもそも景豊本人に、戦国時代の武将らしい野心があったからなのは間違いないのでしょうが、それ以上に少し複雑な事情もあったことが影響していました。
そこで出てくるのが、宗滴の父である敏景の四男で、宗滴の兄に当たる朝倉景総という人物です。
朝倉景総には教景(敏景五男)という弟がいたのですが、景総自身が庶子であったため、異母弟の教景の下座に置かれるという苦渋を舐めていました。
これを恨みに思った景総は、1484年(文明16年)に相撲場にて弟・教景を殺害してしまいます。
ちなみにこの教景は、宗滴とは別人です。
この教景は宗滴の兄に当たる人物であり、この時の宗滴はまだ幼少で、教景とは名乗ってはいませんでした。
当時であればそんなことは無かったのかも知れませんが、後世からすると、同じ名前のひとばかりでややこしいですね。
朝倉氏の歴史の中で、「朝倉教景」を名乗った人物は実はたくさんおり、それだけに重要な名前だった、ということも察せられます。
ともあれ、景総が教景を殺害したことで、教景の養父で朝倉一族の重臣であった朝倉光玖(宗滴が朝倉家の後半を支えた人物ならば、光玖はその前半を支えた一門の重臣でした)は激怒。
景総は光玖の怒りの前に剃髪して許しを乞い、後に両者は和解して景総は一乗谷に出仕し、一門の武将として活躍するようになったとされています。
このように一度は心を入れ替え、1496年(明応5年)の美濃国で勃発した船田合戦への派遣軍の大将を務めたり、自身の娘を従弟で敦賀郡司家の朝倉景豊(ここで景豊に繋がります)に嫁がせたりしていたんですが、かつて殺害した教景の母親である桂室永昌との関係が修復できず、結局越前国を出奔してしまうことになりました。
そういうわけで、景総は朝倉宗家に対して含むところがあった人物、というわけだったのですね。
景豊にとっての義理の父親である景総は、義兄弟の力を借りて朝倉宗家に謀叛を起こすよう唆し、景豊もこの企てに同意することになります。
この企てには当然、宗滴にも声がかけられることになったというわけです。
実は宗滴自身、この景豊の提案はかなり魅力的に映ったらしく、かなり悩んだそうです。
後の世では、朝倉宗家を支えた名将として知られている宗滴ですが、宗滴とて人の子。
若い頃は色々と思うところがあったようで、少なくとも謀反の加担にために声がかけられる程度には、宗家に対する忠誠も微妙だったのかもしれません。
というのは、前述した内容にもあったように、宗滴はその「教景」という名前からも分かるように、嫡男として育てられるはずだったかもしれなかった人物です。
でも実際には長兄であった氏景は後を継いで、そしてこの時代ではさらに家督継承が行われ、その子の貞景が朝倉家当主を名乗っている状況でした。
周囲は当然宗滴に、かつて父・敏景に期待され、嫡男の座すら望まれていたかもしれないことを聞いて育ったはずです。
となれば、甥っ子が当主をやっている現状は面白くないわけで。
宗滴自身、下克上を考えたことは、ごく自然なことだったのかもしれません。
しかし宗滴が評価される所以は、この謀反にどう関わったか、という点でした。
この頃の朝倉宗家の支配はすでに確立しており、当主はまだ若いとはいえ、体制は磐石となっていました。
下克上は容易でない、と冷静かつ正確に判断した宗滴は、最終的に裏切りを回避し、逆に景豊の謀反を貞景に密告することになります。
これによって景豊は失脚し、宗滴はその功によって敦賀郡司に任命されることになったのです。
そしてこれ以降、朝倉宗滴は朝倉宗家を支える存在になっていったわけですね。
要するに、下手を打てば身を滅ぼしかねない謀反のどさくさでうまく立ち回った手腕が、宗滴が軍事的才能だけではなく、政治や謀略の類にも通じていた、という点において評価されることになったのです。
そして宗滴がその最も秀でた軍事的才能を発揮するのが、これからでした。
世にいう、九頭竜川の戦いです。
九頭竜川の戦い

1506年(永正3年)、本泉寺住持蓮悟が檄文を発し、加賀の一向一揆が越前へと侵攻を開始します。
これは越前で起きた一向一揆に加勢する形で、加賀・能登・越中の一向一揆が越前へと侵入したものでした。
いわゆる永正三年の一向一揆のことですね。
この頃、隣国の加賀国はすでに百姓の持ちたる国になっており、一向一揆勢は勢力拡大を狙っていました。
この一向一揆を率いていた本願寺と当時の室町幕府管領・細川政元とは親密な関係で、しかし一方で朝倉氏は反細川派だったものだから、政元は本願寺に要請して反細川派の北陸の諸大名を攻撃させたのが原因といわれています。
越前国を支配する朝倉家は、これを迎撃するために出陣。
この時、朝倉宗滴は他の門徒と朝倉家による連合軍を率い、宗滴は総大将として九頭竜川にて対峙することになります。
朝倉勢8,000~16,000といわれている一方で、一揆群30万。
朝倉家、絶体絶命のピンチです。
織田信長の最初のピンチである今川義元の尾張侵攻ですら、2~4万程度の軍勢だったことを思えば、桶狭間の戦い(織田5千vs今川4万5千)なんて目じゃありません。
楚漢戦争の中で漢軍と趙軍とが井陘で戦い(漢3万vs楚20万。背水の陣の語源となった戦い)勝利に導いた、前漢の国士無双とこと韓信だって、なんのその。
まあ十中八九、30万はさすがに誇張だろうとはいわれてはいますが、しかし一揆勢が大軍だったことは間違いなかったようです。
多勢に無勢な状況ではあったものの、宗滴は機先を制するため、夜半に渡河して一揆軍を奇襲。
これが功を奏して一揆側は敗退。
この戦いを契機にして、朝倉宗滴はその武名を轟かすことになったのです。
各地への転戦
宗滴はこの後も周辺諸国に軍を派遣して、朝倉家の武威を示すことになりました。
1517年(永正14年)、宗滴は若狭守護である武田氏の援軍として出陣。
若狭の逸見氏及び丹後守護代・延永氏の反乱を鎮圧しています。
1525年(大永5年)には、六角氏に協力して浅井亮政を牽制。
五ヶ月に渡って小谷城の一角に陣取り、浅井、六角との調停役を務めたとされています。
ここで義景の代まで続く、浅井氏との盟友関係が生まれたわけですね。浅井家にとっては呪いだったかもしれませんが。
1527年(大永7年)には、幕府の要請で宗滴は養子の朝倉景紀と共に上洛。
川勝寺口の戦いにおいて勝利しています。
ただしこの時援軍を要請した管領・細川高国と宗滴の間に不和があったようで、朝倉軍はさっさと撤退してしまいました。
幕府といった中央からの要請で出陣し、またそれに勝利していったことで、朝倉家の地位向上に努めることができたのは、朝倉宗滴の活躍あってのことだったのは間違いないようです。
朝倉宗滴の最期
1527年(大永7年)になると、宗滴は養子であった朝倉景紀に敦賀郡司を譲ります。
朝倉景紀というのは主君だった朝倉貞景の四男にあたる人物ですね。
1531年(享禄4年)には、加賀の内紛である享禄の錯乱に介入。
そして1555年(天文24年7月21日)、加賀一向一揆を討つために、朝倉宗滴は越後の長尾景虎(上杉謙信)と呼応して加賀に出陣。一気に南郷・津葉・千足といった城を落としました。
しかしこの戦いの最中、朝倉宗滴は陣中において病に倒れ、朝倉景隆に総大将を任せて一乗谷に帰還。9月8日に病没しました。享年79。
この朝倉宗滴の死は、1555年(天文24年)に行われた川中島第二次合戦において、上杉謙信・武田信玄の和睦という形で影響を与えることにもなったといわれています。
朝倉宗滴の評価
朝倉宗滴は朝倉家当主ではなかったものの、実質上の当主といっても過言ではない存在でした。
宗滴は各地に転戦し、戦いに明け暮れるも周辺諸国は朝倉家に対して手出しできず、越前国自体には平和がもたらされ、その全盛期を築くことになります。
軍事方面だけでなく、越後の長尾為景や長尾景虎らとも結んで外交面でも力を発揮していたこともあって、本当に万能な人物だったようです。
宗滴が健在な頃は誰もが越前に手を出せず、越前に平和をもたらした結果、歴代の当主である朝倉孝景(貞景の子)や朝倉義景といった文化に秀でた人物が出たことで、一乗谷に栄華をもたらすことになりました。
結果、当時の一乗谷は北の京とまでいわれるほどまでに発展します。
しかし、朝倉宗滴の存在は大きすぎて、その死により朝倉家が傾いていったことは事実かもしれません。
家臣であった堀江景忠の謀反や一向一揆の激化、織田信長の台頭。
宗滴に代わる人物のいなかった残された朝倉家では、これに完璧に対応することはできませんでした。
そして朝倉義景の代にて、朝倉家は滅亡することになってしまうのです。
後に朝倉家を滅ぼすことになる織田家について、宗滴はその当主であった織田信長について、朝倉宗滴が生前に評価しており、その才能を見抜いていたという逸話が残されています。
「今すぐ死んでも言い残すことはなが、あと三年生き長らえたかった。別に命を惜しんでいるのわけではなく、織田上総介の行く末を見たかったのだ」
臨終の直前に、宗滴が残したとされる言葉です。
朝倉家にとっては、まさに皮肉な結果になったわけではありますが。
また、朝倉宗滴の家臣であった萩原八郎右衛門尉宗俊がまとめたとされる『朝倉宗滴話記』の中に、「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つことが本にて候」という有名な記述があります。
宗滴は戦うことよりも、勝つことを最重視した、戦国時代にあって最も戦国武将らしい存在だったのかもしれません。
朝倉宗滴 関係年表
1477年 朝倉孝景(英林孝景)の八男として誕生。
1481年 父・孝景死去。
1503年 朝倉景豊の謀反。
1506年 永正三年の一向一揆。
九頭竜川の戦いに勝利。
1517年 幕府の命により、若狭・丹後に出陣。
1525年 小谷城へ出陣。
1527年 足利義晴と管領・細川高国の要請で上洛。
川勝寺口の戦いに勝利。
1528年 細川高国との不和により、越前に帰国。
1531年 享禄の錯乱。加賀に出陣。
1548年 朝倉義景が当主になる。
1555年 加賀に出陣。同9月に病死。享年79。






