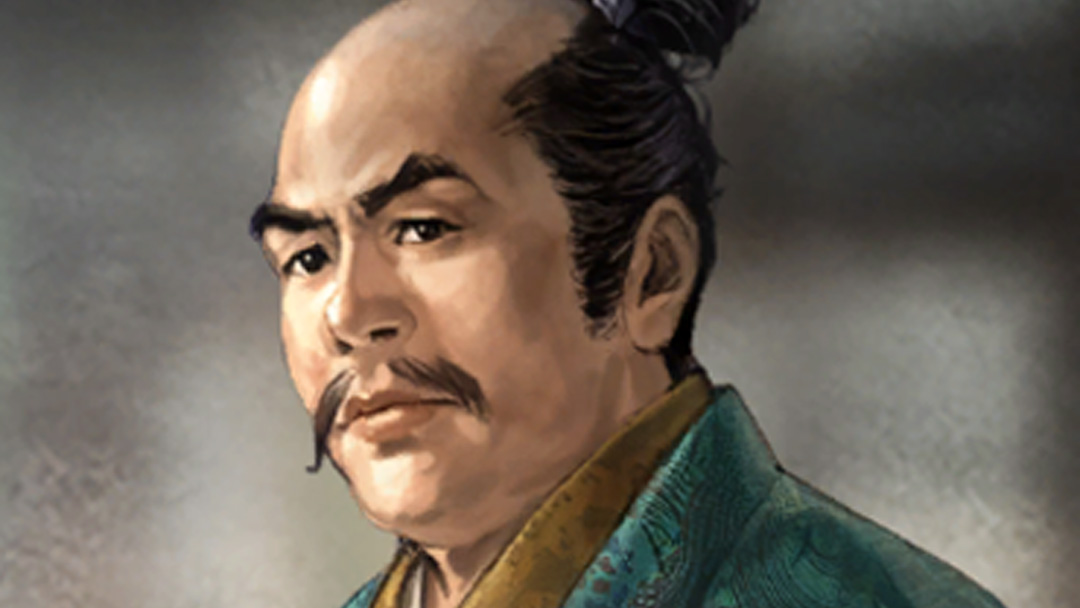朝倉敏景(孝景)【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】

朝倉敏景(朝倉孝景)とは室町時代から戦国時代初期にかけて活躍した武将であり、越前朝倉氏の7代目当主。
天下一の極悪人とも称され、戦国時代の下克上の代名詞ともいえる人物の一人であり、また一乗谷に朝倉氏繁栄の基礎を作りました。
今回はそんな朝倉敏景を、歴史シミュレーションゲームとして有名な『信長の野望』の武将能力から見ていきましょう!
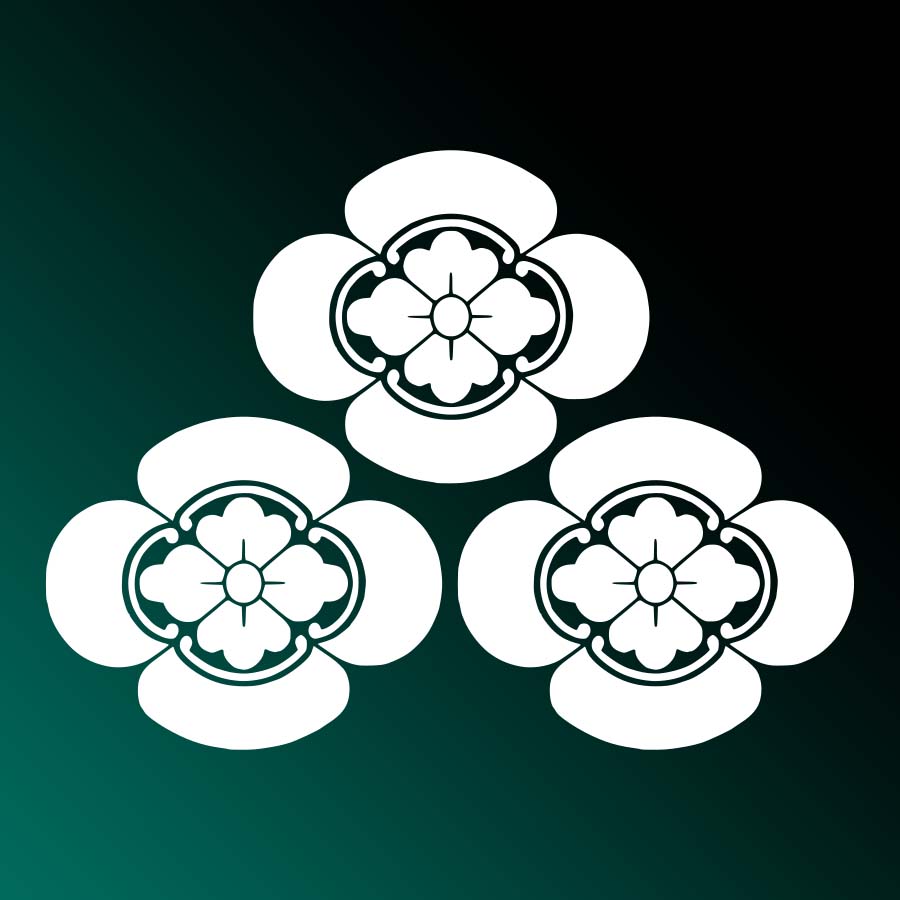 |
|
| 生年 | 1428年(応永35年4月19日) |
| 没年 | 1481年(文明13年7月26日) |
| 改名 | 小太郎⇒教景⇒敏景⇒教景⇒孝景 法名:英林宗雄 |
| 主君 | 斯波義敏⇒斯波義寛⇒斯波義廉 |
| 氏族 | 朝倉氏 |
| 家紋 | 三盛木瓜(みつもりもっこう) |
| 親 | 父:朝倉家景 |
| 兄弟 | 堀江利真室 孝景 経景 輿市郎 景冬 光玖 聖室宗麟 久嶽紹良 定国 |
| 妻 | 正室:朝倉将景娘(円渓眞成大姉) 継室:逸見氏養女・温科氏娘(桂室永昌大姉) |
| 子 | 氏景 景明 孫四郎 景総 教景(以千宗勝) 時景 景儀 教景(宗滴) |
信長の野望での朝倉敏景
信長の野望・蒼天録での能力値
| 信長の野望 蒼天録 | |
|---|---|
| 統率 | 74 |
| 知略 | 85 |
| 政治 | 95 |
……とは息巻いたものの、朝倉敏景は室町時代後期から戦国時代前期の人物です。
つまり、『信長の野望』で網羅している時代の中では、もはや故人であり、登場していないんですよね。(TдT)
主人公である織田信長からみれば、およそ百年前の人物なので当然といえば当然なのですが、これではゲーム的な評価すらみることが叶いません。
と思ったのですが、実はシリーズの中で一作品だけ、特別的な扱いで登場しているんですよね。
それが『蒼天録』です。
それが上記の表の数値というわけですね。
ご覧の通り、かなりの能力値です。
政治などは、95とトップレベル。
このあたりは敏景が政争をうまく潜り抜け、越前一国を手に入れるところまでのし上がったところを、大きく評価されたのでしょう。
納得の数値です。
実は敏景以降の歴代朝倉家当主はみな優秀であり、その片鱗は敏景の曾孫にあたる朝倉孝景(敏景にあやかって同じ名をつけた)からも見て取れます。
また敏景を支えたとされる何人もの兄弟たちも、それぞれが優秀な人物たちでした。
そして極めつけは、敏景の末子であるチート爺様こと朝倉宗滴。
朝倉家はまさに島津家や真田家に勝るとも劣らない、チート一族だったわけですね。
しかし戦国末期にはそれらも枯れ果て、残されたぼんくらの朝倉義景はたった一人でチート主人公・織田信長を相手にすることとなりました。
これでは朝倉家の命運も定まったというもの。
逃げずに名門朝倉家の誇りと共に最期まで戦った義景でしたが、だからこそ憐れだったと言うしかありませんでした。
ともあれ、朝倉家の繁栄をもたらした朝倉敏景。
いったいどんな人物だったのか、はたまたその評価は正当なものか、その人生から紐解いていきましょう。
朝倉敏景とは

朝倉敏景といえば、越前朝倉氏の初代みたいなイメージがありますが、実際には7代目に当たります。
そもそも朝倉氏は、最初から越前国にいたわけではありません。
しかし敏景を初代として数えるなら、最後の当主である朝倉義景は5代目になります。
ちなみにこの朝倉敏景、名乗った名前がたくさんあって、ややこしいことで定評があります。
まず一番最初は教景と名乗り、その後敏景と改名し、再び教景に戻り、最後は孝景という名乗りで落ち着きました。
ややこしいです。しかも同じ名前を名乗っている、別の時代の当主もいたものですから、ごっちゃごちゃです。
例えば一乗谷朝倉氏5代の中では、曾孫にあたる当主も朝倉孝景(朝倉義景の父親)という名前でした。
そのため区別するために、「朝倉敏景」とか、法名から「英林孝景」とか呼ばれて区別されています。
で、この記事では「敏景」で統一しております。
長禄合戦と家督相続
1428年(応永35年)に、朝倉氏6代当主である、朝倉家景の嫡男として誕生しました。
しかし家景は1451年(宝徳2年)に死去したため、朝倉氏5代目当主であった祖父・朝倉教景(この教景という名前もよく出てくる名前なので要注意!)がまだ健在であったことから、この補佐を受け、当主となります。
ちなみに名乗りの一つである敏景という名前は、主君であった斯波義敏より一字を受けて、教景から改名することになったものでした。
しかし1458年(長禄2年)に長禄合戦が勃発。
この戦いは越前守護である斯波義敏と越前守護代であった甲斐常治が起こした一連の戦いのことで、敏景は甲斐常治方につくことになりました。
この長禄合戦で孝景は主君に敵対しこともあって、敏景の名を教景の名に戻しています。意外に律儀?
敏景はこの長禄合戦において、守護代方の主力として活躍しました。
1459年(長禄3年)に行われた足羽郡和田荘での合戦において勝利し、守護方についていた義兄の堀江利真と叔父である朝倉将景を敗死させるなど、その影響力を増していくことになります。
敏景は朝倉家一門において、宗家であり当主の立場にあったものの、父・家景の早死などもあって、その支配体制は磐石ではありませんでした。
家督は祖父・教景の補佐のもと孝景が継承していたものの、朝倉一族の中には反敏景派といった、敏景に従わない者もいたのでです。
このあたりは織田信長の尾張統一期によく似ていますし、戦国時代にあっては特に珍しいことでもありませんでした。
強いものが生き残る、それが戦国時代なのです。
長禄合戦において勝利した敏景は、反敏景派であった一族分家の朝倉将景、朝倉景契、朝倉良景などを討ち果たし、このことで孝景自身の地位を高め、また朝倉氏の台頭のきっかけとなっていきます。
また敏景が味方した守護代の甲斐常治は、長禄合戦の勝利の報を聞くことなく京都で死去。
このことは敏景の影響力が相対的に増す結果にもなりました。
応仁の乱

西軍として活躍
1467年(応仁元年)に、斯波氏の内乱や足利将軍家の家督相続問題、はたまた畠山氏の家督相続問題などが相俟って、世に言う応仁の乱が勃発します。
敏景は主家である斯波義廉と協力して西軍として戦い、御霊合戦、上京の戦い、相国寺の戦いなどに参加。
また伏見稲荷では骨皮道賢を討ち取るといった功も挙げました。
東軍に寝返る
応仁の乱において、西軍の将として活躍していた敏景でしたが、1471年(文明3年)に突如東軍へと寝返ります。
これは魚住景貞を仲介して東軍の浦上則宗と接触し、将軍・足利義政と細川勝元から守護権行使の密約を手にしたことが要因でした。
つまり、越前国の支配権のお墨付きを手に入れたから裏切った、ということですね。敏景の野心家ぶりが伺えます。
応仁の乱のせいで室町幕府の力や各地の守護の力が弱まったことで、その下にいた家臣や国人らが好機が来たとばかりに動き出すのが戦国時代。
敏景はそんな中で、真っ先に動いたわけですね。
まさに機を見るに敏、といったところでしょう。
これは当然、越前一国の支配を念頭においたもので、敏景は越前平定に乗り出すことになります。
そのため孝景は、かつて長禄合戦で味方した守護代・甲斐常治の子である甲斐敏光とも戦うことになっていくのです。
ちなみに敏景が越前に帰ってしまった後の応仁の乱ですが、敏景の寝返りにより東軍が圧倒的優位になったことで、乱は収束に向かいました。
そしてこの東軍の権威を背景に、越前の支配を目指すことになったわけですね。
越前平定戦において、敏景は越前国の西軍勢力を次々に駆逐。
この事態を憂いた甲斐敏光は自ら越前に下向して敏景と戦うも、1472年(文明3年)には敏景が府中を落とし、その後行われた坂井郡長崎庄での戦いにも敏景は勝利し、敏光は加賀に逃亡を余儀無くされました。
しかし1474年(文明6年)になると、富樫幸千代の援助を受けた敏光が再度侵攻。
敏景はこれをよく防ぎ、越前国の形成はすでに朝倉方に傾いていたこともあって、美濃守護代格であった斎藤妙椿の斡旋により敏景と敏光は和睦することになります。
ともあれ敏景はあっという間に越前国を平定してしまったかにみえたのですが、しかし決して完全に、というわけでもありませんでした。
結局敏景は、死ぬまで越前国の平定のために戦うことになるのです。
斯波義寛の朝倉征伐
1479年(文明11年)には尾張・越前・遠江守護である斯波義寛(長禄合戦で孝景が戦った斯波義敏の子)が、敏光を引き連れて越前奪還のために朝倉征伐を開始。
京から進発した義寛は越前北部の坂井郡の細呂宜・長崎・金津にて孝景と交戦。
1480年(文明12年)も戦闘が引き続き、長崎城、金津城、兵庫城、新庄城など朝倉方の城が落とされ、朝倉方は一時窮地に陥ることになります。
この坂井郡での戦いは斯波義寛が優勢であったものの、他の越前各所で行われた戦いでは朝倉方優勢で、一進一退の厳しい戦いが続くことになりました。
そんな中、1481年(文明13年7月)に、敏景は死去。享年54でした。


こんな大事な時に敏景は天寿を全うしてしまうのですが、この頃の人生は人間五十年。寿命には勝てなかったのです。
ではその後の朝倉家はどうなったのでしょうか。
敏景自身が優秀だったことは間違いありませんが、その嫡男だった朝倉氏景も優秀であり、その体制は揺るがずに継承されました。
また敏景の兄弟である経景・景冬・光玖らも有能で、叔父らの協力を得た氏景は斯波勢に対して勝利し、義寛による越前奪還は失敗。
そして氏景は越前国の支配を万全なものにして、越前統一を果たしたのでした。
この頃の朝倉家は人材も豊富で本当に強かったのです。
天下一の極悪人
さて一方で、朝倉敏景は公家や寺社からは蛇蝎の如く嫌われており、天下一の極悪人とまで言われました。
ちなみに言ったのは、公卿であった甘露寺親長です。
これは敏景が公家領や寺社領の押領を頻繁に行ったため、公家や寺社にとって孝景は仇敵であったことに起因します。
甘露寺親長の日記によると、孝景のことを「天下悪事始行の張本」と記している。
孝景の死に際し、甘露寺親長は天下一の極悪人である敏景が死んだことは、近年まれに見る良いことである、とまで書いているほどです。
物凄い嫌われようですね。
しかしここまで悪し様に言われると、むしろ逆に箔がつくかのようです。
とはいえこのことは、越前国平定後に朝倉家にとって大きな禍根となってしまいます。
敏景の行った押領に対抗するために、興福寺別当の経覚は本願寺の蓮如を吉崎に匿い、浄土真宗の布教を許してしまったからです。
これこそが荒ぶる狂気の宗教集団一向一揆発生の原因となってしまいました。
以後の朝倉家最大の敵は間違いなく一向一揆であり、このことは朝倉家の勢力拡大を押さえる一因になってしまいます。
しかし敏景の築いた朝倉家は強く、また歴代の当主は優秀で、さらには敏景の末子だった朝倉宗滴という名将が長生きして頑張ることで、一向一揆に屈することは最後までありませんでした。
朝倉孝景の人物像
戦国時代初期において、下克上を先駆けて行い、天下一の極悪人とまで評された敏景でしたが、朝倉の兵卒には非常に慕われたと伝わっています。
後に朝倉家随一の名将となる八男・朝倉宗滴に劣らぬ軍略を持ち、一方で連歌や和歌にも親しみ、文化人としての素養もあったとされているようです。
また敏景個人の能力が優れていた一方で、彼を支えた朝倉経景、朝倉景冬、朝倉光玖といった弟達の存在も、敏景にとっての大きな力でした。
朝倉孝景によって一乗谷に築かれた朝倉氏の礎は、その後約100年に渡って一乗谷を繁栄させ、11代当主・朝倉義景の代まで続くことになるのです。
朝倉家歴代当主
第1代 朝倉広景 1255年~1352年
第2代 朝倉高景 1314年~1372年
第3代 朝倉氏景(大功宗勲) 1339年~1405年
第4代 朝倉貞景(大心宗忠) 1358年~1436年
第5代 朝倉教景(心月宗覚) 1380年~1463年
第6代 朝倉家景 1402年~1451年
第7代 朝倉孝景(英林孝景) 1428年~1481年
第8代 朝倉氏景 1449年~1486年
第9代 朝倉貞景 1473年~1512年
第10代 朝倉孝景 1493年~1548年
第11代 朝倉義景 1533年~1573年
朝倉孝景 関係年表
1428年 朝倉家景の嫡男として誕生。
1451年 父・家景死去。
1458年 長禄合戦が勃発。
1459年 足羽郡和田荘での合戦にて勝利。
甲斐常治死去。
1460年 今川範将による一揆鎮圧のため、遠江に出陣。
1467年 応仁の乱。西軍として参加。
御霊合戦に勝利。
上京の戦いに引き分ける。
相国寺の戦いに勝利。
1468年 伏見稲荷にて骨皮道賢を討ち取る。
1471年 東軍に寝返る。
1472年 坂井郡長崎庄での戦いに勝利。
1474年 甲斐敏光と和睦。
1479年 斯波義寛による朝倉征伐。
1481年 孝景死去。享年54。