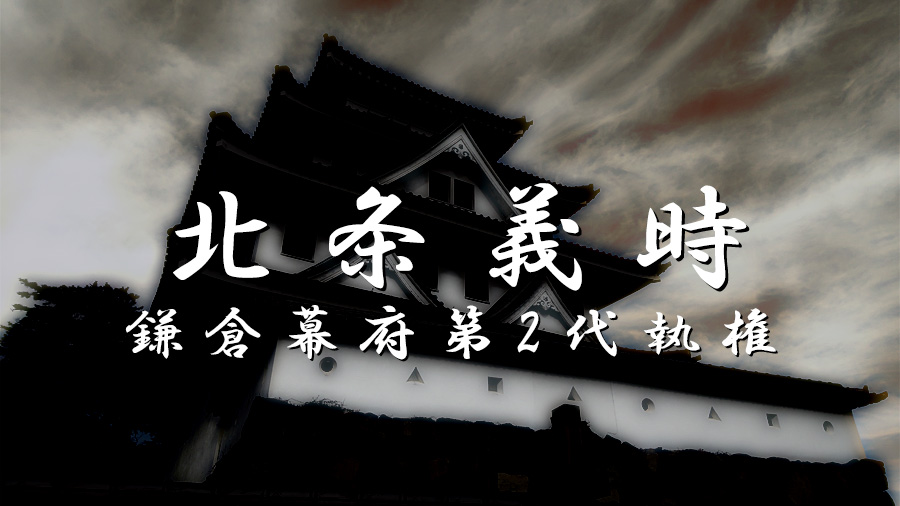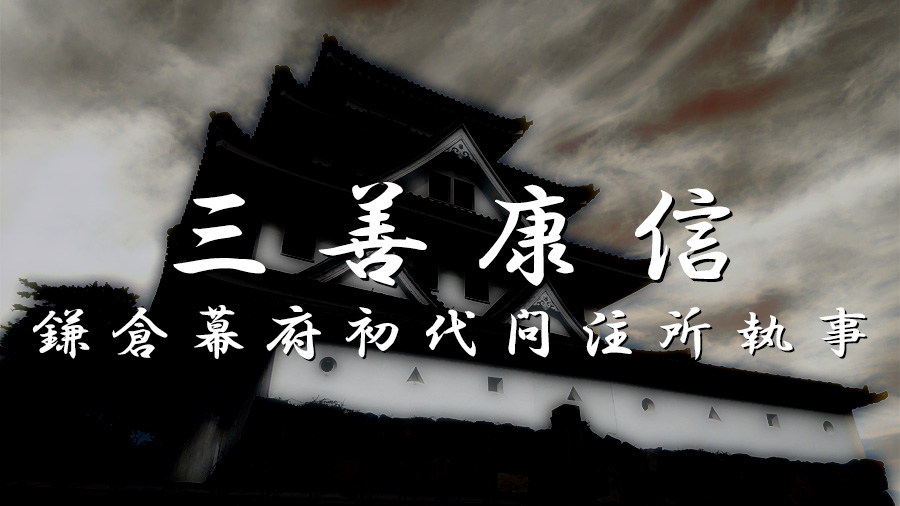大江広元【鎌倉殿の13人が一人、鎌倉幕府政所初代別当】

大江広元とは平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての朝臣。
元は朝廷に仕えていたが、後に鎌倉に下向して源頼朝の側近として仕えたとされています。
鎌倉幕府創設に貢献し、政所初代別当を務めました。
 |
|
| 生年 | 1148年(久安4年) |
| 没年 | 1225年7月16日(嘉禄元年6月10日() |
| 改名 | 中原広元⇒大江広元⇒覚阿(法号) |
| 官位 | 正四位下 明経得業生 縫殿允 少外記 明法博士 検非違使 左衛門大尉 掃部頭 兵庫頭 大膳大夫 陸奥守 |
| 幕府 | 鎌倉幕府政所別当 十三人の合議制 |
| 主君 | 六条天皇⇒高倉天皇⇒安徳天皇⇒源頼朝⇒源頼家⇒源実朝 |
| 氏族 | 中原氏⇒大江氏 |
| 親 | 父:藤原光能? 大江維光? 中原広季? |
| 兄弟 | 親能 広元 章弘 妹(田村(藤原)仲教室) |
| 妻 | 正室:多田仁綱の娘 |
| 子 | 親広 長井時広 那波宗元 毛利季光 忠成 尊俊 水谷重清(猶子) 娘(飛鳥井雅経室) 娘(中原師業室) 娘(藤原公国室) |
大江広元とは
大江広元はみんな大好き戦国時代のひとではありませんが、戦国時代でそこそこ有名ないろんな人物の、ご先祖様だったりします。
例えば江戸幕府において、徳川四天王・徳川十六神将共に筆頭とされ、徳川家康第一の功臣とされた人物。
わかりますか?
そう、徳川四天王筆頭・酒井忠次です。
他には安芸毛利氏で有名な、毛利元就とか毛利輝元もそうですね。
他にも上杉謙信などに仕えた北条高広や景広といった越後北条氏や、安田顕元といった安田氏などもそう。
他にもまだまだいくつか例があったりします。
そんな大江氏の広元は、どんな人物だったのか。
端的にいえば、鎌倉幕府における、将軍に次ぐナンバー2、といった存在でした。
幕府の最高指導者といえば、源頼朝死後は、北条氏、いわゆる第2代執権になった北条義時っていうイメージもあります。
確かに最終的に実権を得たのは義時でしたが、広元は頼朝が生きているうちから官位も他の御家人らに比べて高く、その死後でさえも義時より高い官位を得ていて、名目上ではやっぱり幕府のナンバー2だったといって、差支えは無いと存在でした。
つまり巷でいうところの鎌倉殿の13人――いわゆる十三人の合議制の中でも、一歩抜きん出た人物だった、というわけだったのです。
来歴
大江広元は1148年(久安4年)に生まれたと考えられています。
広元の生年については、『吾妻鏡』や『鎌倉年代記』、『関東評定伝』といった史料によると、1225年(嘉禄元年)に78歳で死去した、という記述から逆算したものになります。
ちなみに『尊卑分脈』では嘉禄元年に83歳で死去したとされていて、そうすると生年は1143年(治2年)ということになりますね。
そして広元の出自に関しては、はっきりとは知られてはいません。
『江氏家譜』によると藤原光能の息子とされ、広元の母親の再婚相手である中原広季のもとで養育されたといわれています。
一方で『尊卑分脈』所収の「大江氏系図」によれば、実父は大江維光であり、養父が中原広季である、となっているのですが、また他方で『続群書類従』所収の「中原系図」によると全くの逆で、中原広季が実父で大江維光が養父となっています。
ちなみに父親かもしれないこの三人ですが、
藤原光能:平安時代末期の公卿。後白河院近臣。平清盛追討の院宣を出させるために白河法皇に取り次いだとか
大江維光:平安時代後期の貴族。権中納言大江匡房の孫。紀伝道の大家だった
中原広季:平安時代末期の貴族。明経道の家系である中原氏出身
略歴はこんな感じです。
とりあえず、広元の父親は貴族だった、ということですね。
広元は当初中原姓を称しており、中原広元と名乗っていたといいます。
現在知られている大江姓を名乗ったは1216年(健保4年)以降のことで、陸奥守に任官した後のことであるとされています。
『吾妻鏡』によると、養父である中原広季に養育された恩はあるものの、衰えいく大江氏の運命を見逃すわけにはいかないから、実父である大江維光の後継者となることを望んだため、とそのように伝わっています。
源頼朝との関係は、まず広元の兄である中原親能が頼朝と親しく、早い段階から京を離れて頼朝に従っていたことに始まったようです。
そして広元は京から鎌倉に下り、公文所の別当となった。
公文所というのは読んで字の如く、公文書を扱う組織のことですね。
この公文所は後に政所として改められるのですが、広元はその政所の別当として朝廷との交渉に当たったといわれています。
別当とは?
別当とは元々は律令制において本官を持つ者が、他の官司の職務全体を統括し監督する地位に就いた時に補任される地位のことをいいます。の組織の責任者、みたいな感じですね。
守護や地頭を設置したのは、広元の献策であると伝わっています。
頼朝死後
1199年(正治元年)に頼朝が死去すると、広元は後家となった北条政子や、第2代執権の北条義時の協調し、幕政に参与したといわれています。
承久の乱が勃発すると、広元の嫡男であった大江親広は後鳥羽天皇の招聘に応じて官軍側に与し、親子で争うことになりました。
この乱において広元は、主戦論を唱えた政子に協調し、官軍を相手に戦うことに慎重であっや御家人たちを鼓舞し、結果的に勝利に導いた功労者の一人であるとされています。
頼朝死後の鎌倉幕府は、権力闘争で有力御家人が次々に失脚したり、将軍である頼朝の血統すら途絶えて、執権の北条氏が最高指導者になっていくことになります。
そんな中でも広元は、うまく処世していきました。
広元は村上源氏の全盛期を築いたとされる源通親こと土御門通親といった公卿との独自の連絡網を持っていたようで、これは頼朝ですら持ち得なかったものらしく、京吏の筆頭というだけでなく、いろんな政策にも関わっており、影響力を行使出来たとされているからでもあるようです。
大江広元に纏わる逸話
・広元の冷静な人物像を指し示す逸話として、「成人してから後、涙を流したことがない」と広元自身が後年に述懐したと伝わっています。
・鎌倉に大江広元の墓とされるものがあるのですが、これは江戸時代に長州藩によって作られたものです。本来の広元の墓は、鎌倉市十二所の山中にある五輪塔であるといわれています。
・承久の乱にて親子相克するこになった大江父子ですが、嫡男・大江親広は戦後出羽国寒河江荘に潜居するも、父・大江広元の死に際して、子の大江佐房に命じて阿弥陀如来を作らせ遺骨を納入し、寒河江荘吉川の阿弥陀堂に安置したとされています。親広自身も没すると、その傍らに葬られました。
大江広元の系譜
・父:大江維光か? – 従四位上、式部大輔。紀伝道の大家。
:藤原光能か? – 正三位、参議。治承三年の政変で一時解任されるが復位。
・養父:中原広季 – 明法博士。
・母:大江維順の娘か?
・正妻:多田仁綱の娘
・大江親広 – 鎌倉幕府の御家人。広元の長男。鎌倉幕府の寺社奉行、補政所、京都守護などを歴任。承久の乱で上皇側に付き隠棲。
・生母不明
・長井時広 – 広元の次男。兄・親広が承久の乱で失脚すると、大江氏の惣領となり幕府中枢で活躍。
・大江宗元 – はじめ宗光と名乗ったという。別名に那波政広。判官代、掃部助。
・毛利季光 – 広元の四男。左近将監、従五位上。評定衆。宝治合戦で自害する。後裔は安芸毛利氏、越後北条氏。
・大江忠成 – 広元の五男。別名・海東忠成。 従四位下、刑部権少輔。評定衆。宝治合戦への加担を問われ辞任。
・尊俊 – 園城寺別当。
・娘 – 飛鳥井雅経室。雅経は従三位、参議。
・娘 – 中原師業?室。師業は従四位下、大外記。中原師兼室とも伝わる。
・猶子
・水谷重清 – 右兵衛尉、伊賀守、正五位下。実は藤原重保の子、妹の子といわれる。
末裔-安芸毛利氏
戦国時代に名を馳せた毛利元就など安芸毛利氏は、大江広元の四男である毛利季光の末裔に当たります。
季光自身は1247年(宝治元年)の宝治合戦により、三浦泰村に味方して三浦一族とともに頼朝の持仏堂であった法華堂で自害。
しかしその四男であった経光は越後にいたことで難を逃れ、所領も安堵されました。
その経光の四男・時親は安芸吉田庄を相続したことで、安芸毛利氏の始祖となったとされています。
これが後の毛利元就や毛利輝元に繋がりました。。
また経光の長男・基親は越後国佐橋荘南条を相続し、ここから越後北条氏が出たとされています。
大江広元画像

大江広元像(大庭学僊画)